[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
忙しい現代人、不規則な生活が原因となる睡眠不足は、大きな悩みです、これを休日に昼近くまで寝て、睡眠不足を補おうとする・・いわゆる寝だめですね!
しかし、これが最近の研究では、寝だめが元で生活のリズムを崩し、健康にも深刻な悪影響を与えることが明らかになってきています!
休日に遅くまで寝て、寝だめをしている習慣の人は、多いのでは?
日常の睡眠不足を休日に寝だめをして、補い疲れを取る・・・・・理にかなった方法に思いますが、本来睡眠は溜めることが出来ないものです、
それに、過剰に睡眠をとった日の夜に、寝付けなかった経験はありませんか?また、寝過ぎは、身体のだるさや頭痛等の弊害が生じることもあります、このように生体のリズムを狂わしてしまうことになるのです!
人間の身体には体内時計なるものが存在して、昼夜のサイクルを感じとり適した睡眠.賞醒のリズムを作り出すのが自然です、
寝だめをすると、このリズムを崩し、夜遅くまで眠気を感じず、結果的に翌日の睡眠時間が短くなる、
これが続くと、日が高くなるまで起きられず、夜更けまで眠れないという症状が出ることがある、これは、概日リズム睡眠障害と呼ばれる症状で、特に夜勤の仕事に就いている人は注意が必要です、
寝だめの弊害として、寝付が悪い・夜中に何度も目覚めるなどの軽い症状から、やがて、10日、1ヶ月と眠れなくなる、不眠症を引き起こすこともあります、
不眠症は、抑うつ状態の原因となる場合が生じます、更にこれが進行すると、深刻なうつ病になり自力で立ち直ることが困難になることもあるので、充分配慮する必要があります!
一般的に睡眠時間は8時間が適当といいますが、ただの目安です、睡眠時間は、各自で違うし、また年齢によっても変化します!10歳代で.8~10時間・成人で6.5~7.5時間、60歳代で6時間程度、このように年齢とともに少なくなるのが普通です。
休日に長く寝るよりも、日常、規則正しく就寝、起床するリズムを保つことが疲れを残さない最適な方法です!
たまには、なかなか寝付けない夜もあるでしょう、こんな時は無理して眠ろうとせず、軽音楽を聴いたり、読書、軽いストレッチ運動などして.寝床に入れば快適な睡眠をえることができるでしょう、
また、寝付けないからといって、寝酒を多量に飲んだり、習慣にするのは良くありません、眠りを促進する効果はあるが、眠りの質を低下して疲れが取れなくなります!
出来るだけ毎日、同じ時間に就寝、同じ時間に起床のリズムを保つことが、良い睡眠を得る最良の方法です・・・♪
- ぐっすり五感熟眠法 ※眠れるCD付き タツミムック

- ¥840
- Amazon.co.jp
- ベッドの上で簡単にできる「寝ヨガ」レッスン〈快眠CD付〉/内藤 景代

- ¥1,100
- Amazon.co.jp
- 枕革命 ひと晩で体が変わる―頭痛・肩こり・腰痛・うつが治る/山田 朱織

- ¥880
- Amazon.co.jp
- 3個同時購入で送料無料☆快適な睡眠を・・・フアモアピロー

- ¥3,129
- セゾン
- マイナスイオンで快適な睡眠を♪ 夢枕

- ¥6,300
- セゾン
なんとなく身体がだるい、疲れる、気力が湧かない等、このような症状は誰でも経験がある症状です、
だるさの原因は、大きく分けると3種類となります
1、.運動や労働等で疲れてだるい・・・コレは原因がはっきりしているので、休養すれば疲れが取れるケースです、
2、休んでもだるさが取れず、また隠れた病気が原因となっている.ケースです、低血圧、貧血、肺結核、肝臓病,糖尿病、腎臓病、内分泌疾患、癌、栄養不足、などが含まれている場合です、
このような場合は、病院で詳しく検査が必要でしょう!
3、原因が精神的なものか?はっきり解らないケースです、病院で診察を受けても何処も悪くないと言われるケースが多い症状です、うつ病、身体表現性障害、気分変調症、慢性疲労症候群等が含まるとされています!
疲れても休む事が出来ない場合が多々あるでしょう、これが長く続くと、休める状況になってもゆっくり休めずまた、やりたい事も出きず、無気力な状態になることが考えられます、
このような時は、出来る事から少しずつやっていく事が大切です!
だるさの治療、対策
1、何時もと違う疲れ、ダラダラと疲れが取れない、発熱や下痢などの症状が.ある場合は、何らかの疾患が原因の可能性が高いので病院で診察を受けましょう、
2、休養、
ゆっくり休むことが大切です、これで疲れが改善されれば、一時的なもので問題はありません、
3、睡眠と、生活リズムを整える、
4、だるさの原因を考え、思い当たる事があればこの対策を行う、
5、気分転換をしよう
軽い運動、散歩、入浴などは身体と心の緊張を解すのに適しています、
6、栄養のバランスを考慮して、規則正しい食事を実行する、
- 体に効く!酢をおいしくたっぷり食べるレシピ―血液サラサラ、疲労回復、ダイエットに!/落合 敏
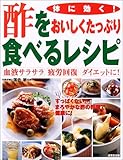
- ¥1,155
- Amazon.co.jp
- 足裏のツボ健康法―ボケ予防・疲労回復 治癒力・回復力を高め老化も予防する「第2の心臓」足の裏/安東 春樹
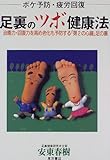
- ¥1,785
- Amazon.co.jp
心の健康を保って、快適な日常を過しましょう!
心の健康を保つ為の必要なことは?
1、充分な休養と睡眠をとりましょう!
2、身体が資本です、病気を予防して元気に過す、
3、趣味など自分だけの為に時間をもとう、
4、ストレスを溜めない、発散する事が出来ることをもっている(遊び・趣味等何でも可)
5、心から信頼できる家族、友人、知人がいる、
6、職場、近所付合い等、良い人間関係が維持できる、
7、困った時、行くことが出来るまた、帰る場所がある
8、バランスのとれた生活をしている、(仕事、遊び・運動・休養等)
気持ちの問題は!
1、心にゆとりを持って、目標,希望を抱いて過している、
2、心に柔軟性があり、何かトラブルがあっても自分を見失いで平常時の自分に戻れる、
3、理性と欲求、自信と謙虚さ、思考と感情などバランスのとれた考えが持てる、
4、マイナス思考でなくプラス思考に物事を考える事が出来る、
5、自尊心や信頼感を保つ事が出来る、
6、愛の心を持っている、
7、内面的な自分自身と戦っている!
上記事項で欠けている事があれば改めよう、
心の健康を回復させ、強い心を持って過す事が出来るようになるでしょう!
↓・・・心の健康を取戻そう!
- 食事で治す心の病―心・脳・栄養 新しい医学の潮流/大沢 博

- ¥1,260
- Amazon.co.jp
定期健診断等で高脂血症・・・と言われた方は多いのでは?近年高脂血症者は増えているそうです、
高脂血症とは
血液中に溶けている脂質が必要量より過剰な状態です、これはコレステロール値や中性脂肪値が高い状態なのです!
質には、コレストテロール、リン脂質、中性脂肪、遊離脂肪酸などがあります、
異常に高くなっても,殆ど自覚症状が無いのが普通です、
1、中性脂肪が高い(150mg/dl以上)
2、総コレストロール値が高い(220mg/dl以上)
3、両方とも高い
以上の3タイプに分けることが出来る.
高脂血症は、自覚症状が無いので、治療せずにそのまま置きがちですが、動脈の内壁にコレステロールが沈着し動脈の弾力性が減少し硬くなったり、血管が狭くなり血流が悪くなり、動脈硬化が進行します、
更に進行すると、心臓や脳続いている血管の血流が悪くなったり、詰まったりする、脳梗塞や、心筋梗塞、狭心症など怖い病気が発病する危険度が増します、・・・注意!【総コレストロール値が300mg/dl以上の人は特に注意】
コレステロールには善玉(HDL)と悪玉(LDL)があります、
善玉は、動脈の内壁に付着したLDLコレステロールを除去して動脈硬化を防ぐ働きをします。
高脂血症の原因は食事深い関係があります、食事を改善するのが予防対策となる!
動物性食品(卵の黄味、肉の脂身、魚卵、ウニ、イカ、エビ、バター等)に比較的多く含まれている飽和脂肪酸やコレステロールは、総コレステロール値を高くする作用があります、
逆に、植物性の油や魚に多く含まれる多価不飽和脂肪酸は、血中の総コレステロールが上がるのを抑える働きがあります、
繊維分の多い食べ物(コンニャク、芋、海草類、キノコ類等)は、コレステロールを体外に出しやすくします、野菜、大豆製品(豆腐等)は毎日食べると良い!
また、パン、酢等に使われている紅麹は、コレステロール値を下げる効果があるのではと、言われているそうです、
肥満の人は、ダイエットが必要でしょう、
遺伝的に素質が関与する場合もあるので、異常に高い人は精密検査を受ける必要があります。
爪の病気・・ありそうに無いが?有るのです、
1、一番多いのが、爪水虫(爪白癬)です、
健康な爪はピンク色をしていますが、爪白癬になると白く濁り分厚くなり、もろくなります、
これは白癬菌(カビの一種)で起こります、爪の主成分のケラチンを餌として繁殖するので、そのままにしておくと爪がボロボロになってきます、治療すれば完治出来るので、早めの治療を行いましょう、
2、爪甲剥離症
名前のとおり、爪が爪床から剥離される症状です、剥離した箇所は、黄白色に変化してきます、
指先を多く使うことをしたり、水仕事が多い場合にが原因です、また、洗剤などの化学成分も原因の一つと言われています、
3、爪囲炎
爪の周囲の炎症は、カビや細菌、ウイルスなどの感染症が殆どです、
多いのがひょうそ呼ばれる症状です、これは傷などから菌が入り化膿して赤くはれて痛みを伴います、
爪の周りに炎症がある場合は、常に手を清潔にし、乾燥させておくことが予防となります。
爪のトラブル、
1、陥入爪
爪の先端の両側が、周囲の皮膚に食い込んで傷つけ、痛みを伴います、これは足の親指に起こりやすい!
この原因は、深爪です、・・・爪を切る時は、指先より僅か長めにしておけば問題ないでしょう!
2、巻き爪
爪が長い時に靴等を履けば、爪甲が先端が湾曲し、爪床の皮膚を挟んだり食い込んだりします、これもひどくなれば歩くことも困難になるほど痛みを伴う場合が生じます、
治すには、曲がった爪を切り、靴は先端にゆとりがあるものに変えることです、一時的に症状が改善しても再発することもあるので、・・・爪が湾曲を抑える処置が必要です!
爪は病気の警報機―毎日一回、「じっと手を見る」健康診断/東 禹彦

- ¥870
- Amazon.co.jp
- 三週間で水虫は治る―ケラチン除去方式/中村 徹司

- ¥1,365
- Amazon.co.jp

